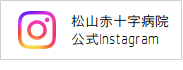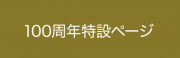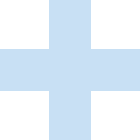
初期臨床研修医
救急医療・急性期医療・一般医療の3領域を、
確実に学べるのが何よりの魅力。
自分の進路を多様な経験の中で確認できます。

救急部
1.診療科紹介
救急部は輪番制の救急当番日に、二次救急の「初期診療」と「入院診療」を担当するとともに、救急日以外の救急患者の初期診療に当たっています。臨床研修の視点から再構築された体制が特徴で、常に研修医が主体となって、救急研修の目標「症状と身体所見、簡単な検査所見に基づき、鑑別診断、初期治療を的確に行う能力を獲得する」を短期で達成できるように様々な配慮を行っています。曜日を問わず救急科専門医と一緒に初期診療を行うことで、救急対応能力がめざましく向上します。また、他科専門医の指導も受けながら、頻度の高い救急疾患の入院も担当することで幅広い知識を習得できます。
2.指導スタッフ
| 指導責任者 | 森實 岳史 |
|---|---|
| 指導医 | 上田晃三、前川奈々 |
3.一般目標(GIO)
緊急を要する病態・疾患・外傷を幅広く経験し、適切な初療ができるための基本的能力を習得する。
4.行動目標(SBO)
(1)救急部診療録に基づいた、論理的な臨床推論の考え方を習得する。
(2)バイタルサインを的確に把握し重症度・緊急度を判定でき迅速・的確に対応できる。
(3)ショックの診断と治療ができる。
(4)二次救命処置(ICLS)を適切に実施でき、一次救命処置(BLS)を指導できる。
(5)頻度の高い救急疾患の初療を適切にできる。
(6)救急診療に必要な精神的・心理的反応を理解し、適切な対応が出来る。
(7)専門各科への適切なコンサルテーションができる。
(8)チーム医療を理解し参画することができる。
(9)地域の救急体制(輪番制、精神科救急)を理解し、個々の患者の事情に応じた適切な対応が出来る。
(10)災害時の救急医療体制を理解し、非常時の対応を把握している。
5.方略(LS)
カンファレンス
Daily conference
| 日時場所 | 平日9:30(救急日は8:15)病棟カンファレンスルーム |
|---|
- 救急部の入院患者に関して問題点の検討、治療方針決定を行う
救急入院カンファレンス:入院患者の紹介、割り振り
| 日時場所 | 救急日翌日8:45 カンファレンスルーム(休日は9:00) |
|---|---|
| 参加者 | 救急部指導医・研修医、内科レジデント、内科系各科救急指導医など |
| 方法 | 病棟当直担当医から入院患者紹介、専門性に基づき担当科または担当研修医を決定 |
救急部カンファレンス
| 日時場所 | 救急日と救急日の翌日を除く金曜日12:00 大会議室 |
|---|---|
| 参加者 | 研修医全員、救急部指導医、各科指導医、直前の救急外来当直医 |
| 方法 | 研修医が外来担当時や入院診療で判断に迷った症例を最低1例提示、問題点を討議 |
救急部勉強会
- 不定期症例検討会
外来業務(OJT)
救急日
| 日勤帯 | 指導医と救急外来で初療に当たる |
|---|---|
| 翌朝 | 救急入院カンファレンスで時間外入院患者の担当医となる。 |
救急日(休日)
| 日勤帯 | 指導医と救急外来で初療に当たる |
|---|---|
| 翌朝 | 救急入院カンファレンスで時間外入院患者の担当医となる。 |
救急日以外の平日日勤帯
- 指導医と救急外来で救急患者の初療に当たり、「経験すべき症状・病態」に該当する患者の初期診療を行う。
救急日以外の時間外
- 当直医等の指導で適宜救急患者の診療に当たる。
病棟業務(OJT)
- 受け持ち患者を回診し、問題点を指導医と検討し、検査や投薬、処置指示を行い、診療記録を作成する。
- 指導医に記載内容の承認を受け、問題があれば修正を受ける。
チーム医療への参画
- 褥瘡ケアチーム(褥瘡回診;毎週水曜14:00~)
- 栄養サポートチーム(NST回診;毎週火曜13:30~)
- 認知症ケアサポートチーム(DST回診;毎週月曜13:00~)の回診に参画する。
6.評価
- 形成的評価:毎日
Daily conferenceと外来・病棟OJTに基づき、行動目標と経験目標の視点から研修医にフィードバックを行う。ローテート終了時には研修医・指導医の相互評価を行い、総括的評価の指標とする。 - 総括的評価:ローテート終了時
研修医はPG-EPOCに入力、指導医が確認して到達度を測定する。必要に応じて研修方法の見直しを行う。形成的評価も勘案し目標の8割程度に到達した場合に合格とする。